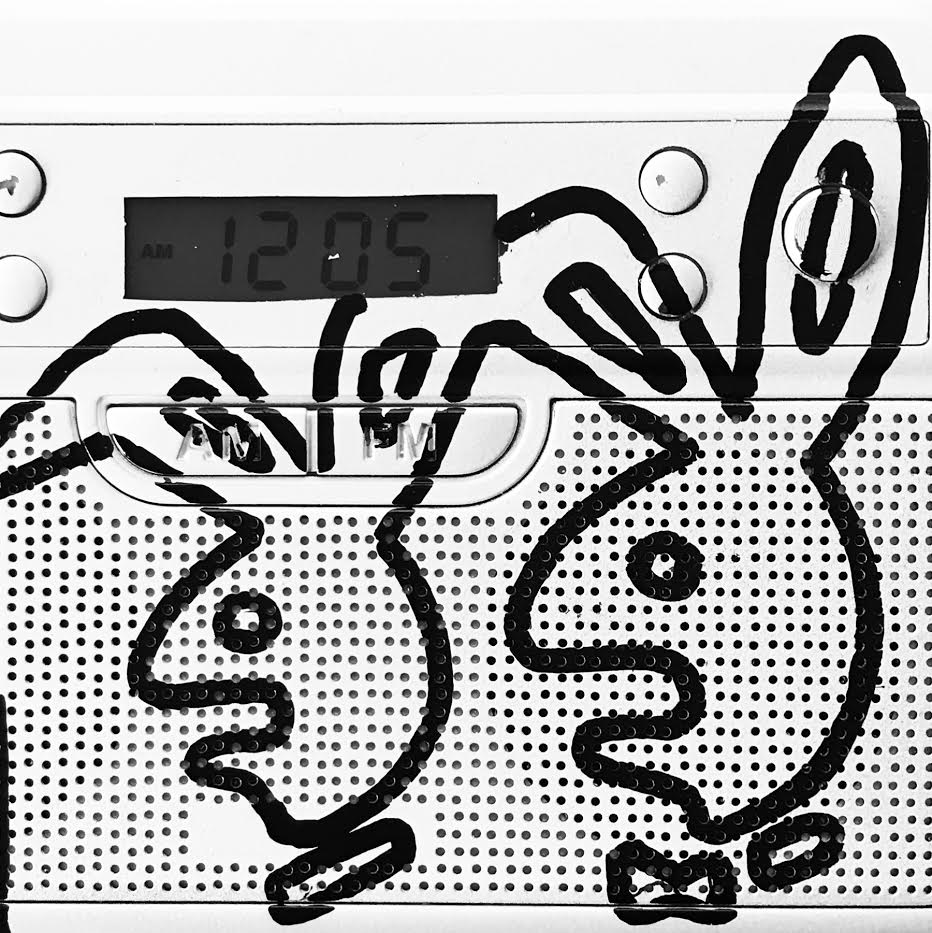ながい、ながい夢をみた。
その中ではかつての同級生たちと知らない顔を含む数名が同じバスに乗っていた。外の景色は暗かった気がする。夜だったのかもしれない。
もう10年以上前になるだろうか。自死してしまった小・中の同級生であるKがなぜか同乗していた。トトロに出てくるネコバスみたいな柔らかなソファが、バスの内側をぐるっと囲む。私が今まで出会った、でもきっと知らない人同士が楽しそうにおしゃべりしている。一体私たちはどこへ向かっているのだろう。
少し離れた場所にいたKに、私は思わず声をかけた。「K!久しぶり~元気だった?」。彼は笑いながら近づいてきた。「おお~久しぶりじゃん!元気元気」。そこからたわいもない話を延々と続け、私たちを含む同級生は久しぶりの再会に笑い合った。ずっとこの時間が続けばいいと思った。きっと夢の中の自分も同級生たちも、これが夢だと理解していた。どんなに望もうとも永遠に取り戻すことのできない時間。
彼は勉強ができるタイプではないし、足も速くはなかったけれど、いつも学芸会のヒーローだった。歌がうまくて、どんな楽器だってすぐものにする。特に得意だったのはドラム。演技力も突出していて、彼が舞台に立つだけで空気が一瞬にして変わった。誰もが毎年彼が何をどんな風に演じるかを楽しみにしていた。だからいつも主役は彼以外考えられなかった。そういった稽古に通っていたわけではない。もちろん学芸会に向けて練習はしていたが、秀でた才能があった。そして、歌うことや演技が心底好きだったのだと今改めて思う。身体ひとつで誰かを喜ばせることに幸せを感じていたのだと。
小学校の卒業式の日、入場する前に校舎と体育館を繋ぐ寒い廊下で私たち卒業生は待機していた。これからも同じ教室で肩を並べるから最後だという実感もないけれど寂しさや不安が押し寄せ、未来にほんの少しの期待を膨らませていたあの日。窓の外には雪がしんしんと降っていた。
突然誰かが言った。「K、なんか歌ってよ」。
ざわざわしていたその場がそっと静まる。
七回目のベルで受話器を取った君 名前を聞かなくても声で すぐ分かってくれる
歌い出したのは、当時ヒットしていた宇多田ヒカルの「Automatic」。そのとき、淀みが晴れていくさまを私たちは強く感じた。拍手喝采。体育館で待機する在校生は、突然聞こえてきた拍手に何事かと思ったことだろう。
また会いたい、また声が聴きたいといくら願ってもーーこの世界での再会という奇跡のシナリオは用意されていない。違う世界で彼が笑って生きているのならそれでいいと、やっと思えるようになった。みんなもそうだろうか。でも、彼を苦しめ死に追いやった人たちを私たちは二度と許すことはできない。
彼は私たちに何を伝えようとしてくれたのか。直接受け取ることのできないメッセージに自問自答しながら、夢と記憶の狭間を行き来する。
ふと目元に明るい光を感じ、カーテンを開けた。私は、好きなことをしながら生きていくために選択を繰り返してきた。何不自由なく“好き”を“好き”でいられる日々に、思いを巡らせた。