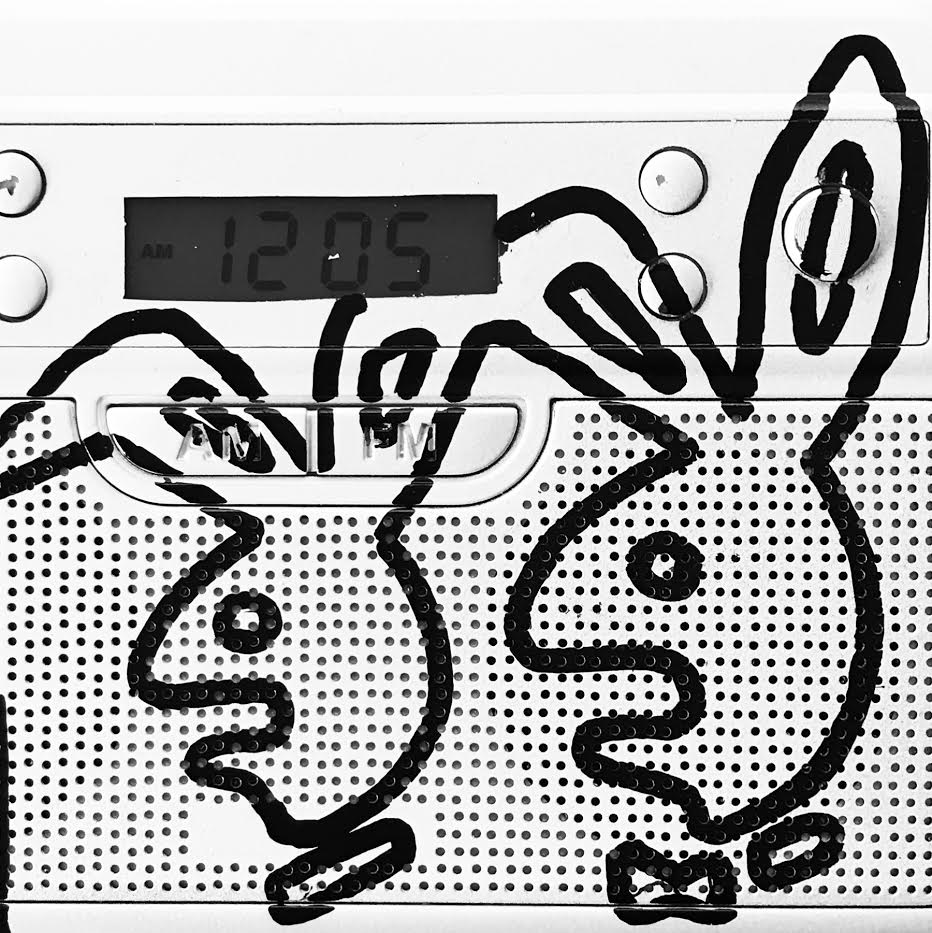今年は年明けから現場、現場、現場。






もう形になったものもありますが、春に向けて複数のプロジェクトの準備が進んでいます。
そしてその合間に本。
現役の学校の先生とその仕事についてポッドキャストで話さなければいけないことになり、教育者と渡り合える知識なんて少しもないので付け焼き刃でもといくつか興味のあった本をかき集めてダッシュで読みました。
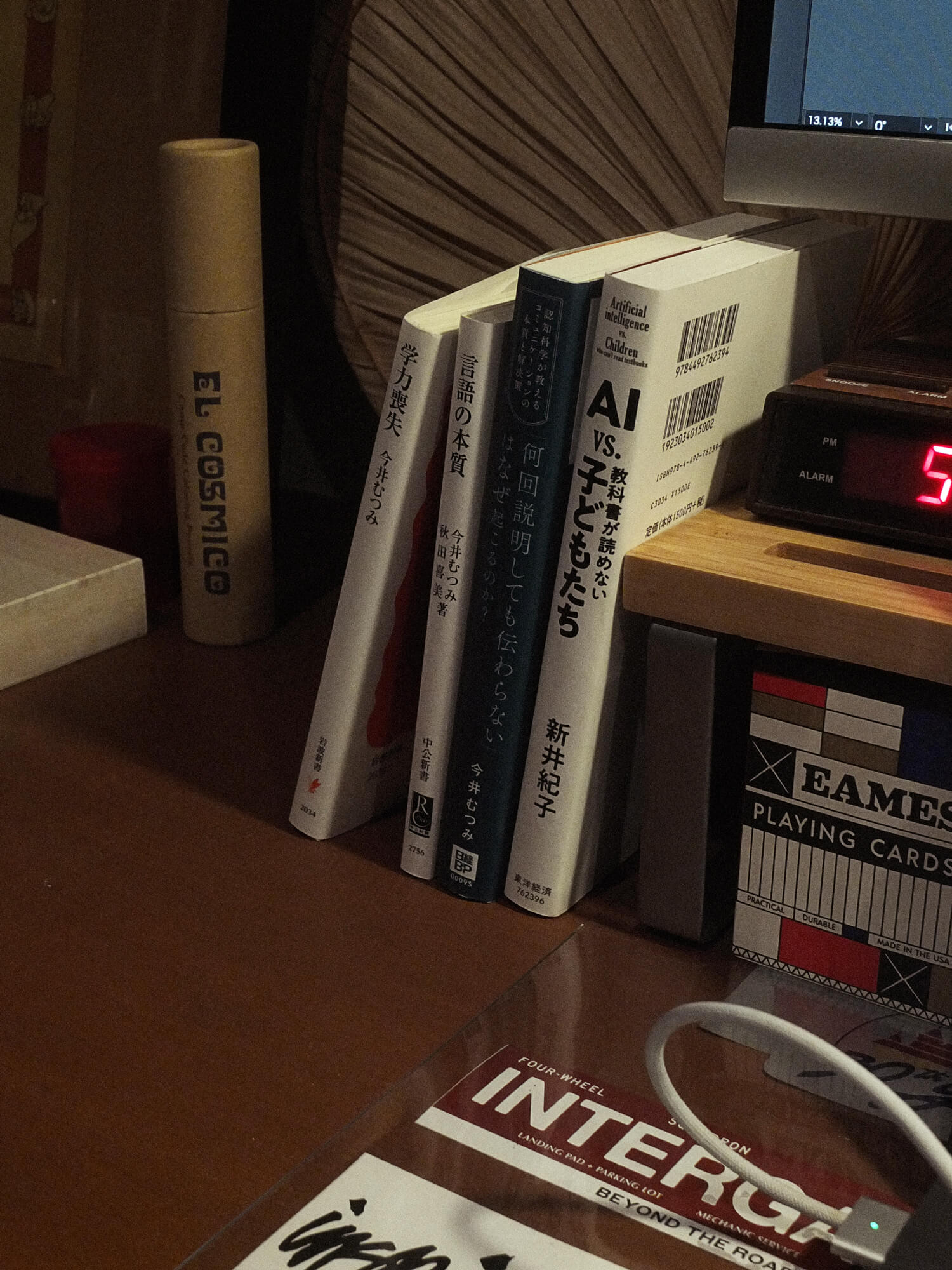
意外と日々の仕事への示唆に富んでおります
あげられている課題はどれも遠いところの話ではなく、かなり距離感の近い、自分ごととして捉えずにはいられないことばかり。中学校までの学習のことが題材のほとんどなので、そりゃそうか。なんだかいまの教育についてしっくりこない感覚や課題感を持たされながら先生との会話に突入。
でも実際先生とポッドキャストの収録に臨んでみると本の内容と先生の考え方が異なる点も多くて、そっちはそっちで視点次第で正解が違うようだなという学びにもなりました。まあ多少本を読んだ程度の理解では結局踏み込みきれないところもあって、話し相手としては全然不足、反省です。
それよりこれらの本を読んで面白かったのは、年末年始に会った親戚のちびっ子たちの発する不思議な日本語のメカニズムが少しわかったことでした。
どうしてそういう構造の文になる??という謎発言にも子どもなりの理由や規則があって、大人の言語ルールにまだ縛られていない時期の稀有な言動をこちらも楽しむべきみたいです。


件のポッドキャストの中では学生時代になぜ勉強をしないといけないか、について話し合う場面もありました。先生からは全く違う視座での答えをいただいたけど、それについてしばらく考えるうち、マネタイズしなくてもいいただの勉強を自分の裁量でできる学生という身分の特権性を改めて感じるようになりました。
大人になってからも勿論勉強はできたけど、大人という本格コースに入る前の失敗しても死なない練習コースでもっと幅広く、精度の高い勉強や経験や意味ある失敗ができるなら、本格コースでの振る舞いやスコアも変わってくるだろうに。
と思いつつ、いま厳しい状況におかれている「教師」の方々にもっと精度高くよろしくねと言う訳にもいかんというのが実際のところ。大人になってから「もっと学生時代に楽しく勉強しとけばよかったな」と多くの人が思うのを、同じ解像度で生徒に伝えられたらいいのにね。と話しましたが、それもまた難しいようで。